生成AIからAIエージェントへの進展
ChatGPTなどの生成AIを使って議事録を要約したり、外国語で書かれたレポートの要約や翻訳、プレゼン資料の構成の検討を頼んだりなど、生成AIは多くのビジネス現場で活用され始めています。これまで作業者が目で確認し、手作業でしていた業務が短時間で終わるようになり、生産性が向上したことや、仕事の質が変わったことを感じている人も多いのではないでしょうか。
生成AIが登場したばかりのときは、過去のインターネット上にある文書を中心に作られた大規模言語モデル(Large Language Model)内の情報をもとに回答していたため、最新の情報を検索することはできませんでした。また、社内にある文書の内容を利用した回答を作成することもできず不便に思うこともありました。
その後、生成AIを利用したサービスは進化し、最新情報を検索できるようになりました。なかでもDeepResearchという強力な調査機能では、十数分で最新の技術動向や技術のユースケースについて、かなり精度の高いレポートを、出典情報付きで出力できます。
日々進化していく生成AI技術ですが、使っていて不満に思うことがないわけでもありません。
・「言われたこと」にしか対応できない
・複数ステップにわたるタスクを処理できない
・状況を把握しながら自律的に判断することができない
などがそれにあたります。
こうした生成AIの限界を乗り越える存在として登場してきたのが、AIエージェント(AI Agent)と呼ばれる新たな技術です。ではAIエージェントとはどのようなものか見ていきましょう。
生成AIが登場したばかりのときは、過去のインターネット上にある文書を中心に作られた大規模言語モデル(Large Language Model)内の情報をもとに回答していたため、最新の情報を検索することはできませんでした。また、社内にある文書の内容を利用した回答を作成することもできず不便に思うこともありました。
その後、生成AIを利用したサービスは進化し、最新情報を検索できるようになりました。なかでもDeepResearchという強力な調査機能では、十数分で最新の技術動向や技術のユースケースについて、かなり精度の高いレポートを、出典情報付きで出力できます。
日々進化していく生成AI技術ですが、使っていて不満に思うことがないわけでもありません。
・「言われたこと」にしか対応できない
・複数ステップにわたるタスクを処理できない
・状況を把握しながら自律的に判断することができない
などがそれにあたります。
こうした生成AIの限界を乗り越える存在として登場してきたのが、AIエージェント(AI Agent)と呼ばれる新たな技術です。ではAIエージェントとはどのようなものか見ていきましょう。
AIエージェントの“自律性”を支える技術
AIエージェントとは何でしょうか。AIは人工知能、エージェントは代理人という意味を持ちます。人工知能が代理人の役割を果たす、とイメージしてください。AIエージェントは、利用者から与えられた目的に対して、必要な情報を取得し、ツールを使いこなし、複数ステップの処理を自律的に実行するAIシステムと定義できます。
生成AIが「言語で出力する存在」だったのに対して、AIエージェントは私たち利用者の代理として、「タスクを遂行する存在」と言えます。では、何がこの違いを支えているのでしょうか?
以下に、AIエージェントを実現する要素技術のうちのいくつかを簡単に紹介します。
・Retrieval-Augmented Generation(RAG):外部知識の活用
生成AIの回答は学習時点の大規模言語モデルにある知識に依存しますが、RAGを用いることで生成AIが学習していない情報を利用することができます。生成AIが学習していない社内文書や外部データベースから最新の情報を取得し、それをもとにユーザーのタスクに有効な情報を生成できます。RAGは、ハルシネーションという、AIが「幻覚(事実に基づかない出力)」を起こすリスクを軽減するうえで不可欠な技術です。
・機能呼び出し(Function Calling):実行力を持つAI
従来の生成AIはテキストしか出力できませんでしたが、機能呼び出しを使うことで、普段利用しているスケジュール管理ツールに予定を登録したり、Excelを操作したり、APIにアクセスして社内外のデータを取得したりといった「行動」が可能になります。この仕組みによって、AIは単なる会話相手から、「実務を代行する代理人」に進化しました。
・ReAct:推論→行動→観察のループ構造
ReActは、Reasoning + Acting の略です。Reasoningは推論、Actingは行動です。ReActは、AIが「推論し → 行動し → 結果を観察してまた推論する」というループ構造を実現する仕組みです。たとえばAIに10,000文字の文書を800文字に要約する指示を出したとします。ところが、AIエージェントは分かりやすさを重視したため、最初の要約は2,000文字になってしまいました。これでは指示に対して文字数が多すぎるため、さらに要点を絞り800文字の要約を完成させることができます。ReActのない通常の生成AIでは、AIエージェントが行う試行錯誤がされません。利用者の単一の指示に従い即時に回答を生成するため、AIエージェントが重視したわかりやすさが若干省力された回答が生成されると思われます。
このように、「推論→行動→観察」の繰り返しによって、AIは1回で利用者の指示を出力するのではなく、状況に応じて試行錯誤しながら精度を高めていくことができます。
・永続メモリと履歴の保持:文脈の理解をサポート
さらに高度なAIエージェントでは、会話の履歴や過去の指示を記憶し、文脈を理解したうえで判断や行動が可能です。こうなってくると本当に秘書のような存在になりますね。AIエージェントが賢く機能するためには、過去の会話や知識、処理履歴を憶えておく仕組みが必要です。これを永続的メモリと呼び3種類に分類できます。
-エピソードメモリ(短期的なやりとりの記憶)
直前の会話や処理内容など、直近の出来事を一時的に憶えておくメモリです。
たとえば、会話のなかで「この会社の売上を教えて」と聞いた後に、「では利益率は?」と聞いても、どの会社の数値を出すのかをAIエージェントが理解できるのはエピソードメモリのおかげです。
-セマンティックメモリ(知識の記憶)
業務知識や規則、社内ルールなど、繰り返し使う“意味のある情報”を比較的長期的に憶えておくメモリです。たとえば、「当社の営業サイクルは3か月ごと」、「顧客との合意はこの社内稟議では必要」といった、業務の前提知識を保持してくれます。
-ベクトルメモリ(検索用の記憶)
大量の文書やデータをAIが意味ベースで検索できるように整理・保持するメモリです。たとえば、過去の議事録のなかから「〇〇という考えに近い発言があった資料」を探すとき、文字列ではなく意味の“近さ”で探せるのがベクトルメモリの役割です。これにより、同じ業務を何度も繰り返すたびに、AIが“賢くなっていく”という体験が可能になります。
こうした技術が連携することで、AIエージェントは単なる自動化ツールではなく、「業務を委任できる存在」として現れはじめているのです。
生成AIが「言語で出力する存在」だったのに対して、AIエージェントは私たち利用者の代理として、「タスクを遂行する存在」と言えます。では、何がこの違いを支えているのでしょうか?
以下に、AIエージェントを実現する要素技術のうちのいくつかを簡単に紹介します。
・Retrieval-Augmented Generation(RAG):外部知識の活用
生成AIの回答は学習時点の大規模言語モデルにある知識に依存しますが、RAGを用いることで生成AIが学習していない情報を利用することができます。生成AIが学習していない社内文書や外部データベースから最新の情報を取得し、それをもとにユーザーのタスクに有効な情報を生成できます。RAGは、ハルシネーションという、AIが「幻覚(事実に基づかない出力)」を起こすリスクを軽減するうえで不可欠な技術です。
・機能呼び出し(Function Calling):実行力を持つAI
従来の生成AIはテキストしか出力できませんでしたが、機能呼び出しを使うことで、普段利用しているスケジュール管理ツールに予定を登録したり、Excelを操作したり、APIにアクセスして社内外のデータを取得したりといった「行動」が可能になります。この仕組みによって、AIは単なる会話相手から、「実務を代行する代理人」に進化しました。
・ReAct:推論→行動→観察のループ構造
ReActは、Reasoning + Acting の略です。Reasoningは推論、Actingは行動です。ReActは、AIが「推論し → 行動し → 結果を観察してまた推論する」というループ構造を実現する仕組みです。たとえばAIに10,000文字の文書を800文字に要約する指示を出したとします。ところが、AIエージェントは分かりやすさを重視したため、最初の要約は2,000文字になってしまいました。これでは指示に対して文字数が多すぎるため、さらに要点を絞り800文字の要約を完成させることができます。ReActのない通常の生成AIでは、AIエージェントが行う試行錯誤がされません。利用者の単一の指示に従い即時に回答を生成するため、AIエージェントが重視したわかりやすさが若干省力された回答が生成されると思われます。
このように、「推論→行動→観察」の繰り返しによって、AIは1回で利用者の指示を出力するのではなく、状況に応じて試行錯誤しながら精度を高めていくことができます。
・永続メモリと履歴の保持:文脈の理解をサポート
さらに高度なAIエージェントでは、会話の履歴や過去の指示を記憶し、文脈を理解したうえで判断や行動が可能です。こうなってくると本当に秘書のような存在になりますね。AIエージェントが賢く機能するためには、過去の会話や知識、処理履歴を憶えておく仕組みが必要です。これを永続的メモリと呼び3種類に分類できます。
-エピソードメモリ(短期的なやりとりの記憶)
直前の会話や処理内容など、直近の出来事を一時的に憶えておくメモリです。
たとえば、会話のなかで「この会社の売上を教えて」と聞いた後に、「では利益率は?」と聞いても、どの会社の数値を出すのかをAIエージェントが理解できるのはエピソードメモリのおかげです。
-セマンティックメモリ(知識の記憶)
業務知識や規則、社内ルールなど、繰り返し使う“意味のある情報”を比較的長期的に憶えておくメモリです。たとえば、「当社の営業サイクルは3か月ごと」、「顧客との合意はこの社内稟議では必要」といった、業務の前提知識を保持してくれます。
-ベクトルメモリ(検索用の記憶)
大量の文書やデータをAIが意味ベースで検索できるように整理・保持するメモリです。たとえば、過去の議事録のなかから「〇〇という考えに近い発言があった資料」を探すとき、文字列ではなく意味の“近さ”で探せるのがベクトルメモリの役割です。これにより、同じ業務を何度も繰り返すたびに、AIが“賢くなっていく”という体験が可能になります。
こうした技術が連携することで、AIエージェントは単なる自動化ツールではなく、「業務を委任できる存在」として現れはじめているのです。

AIエージェントが実現する金融サービス
AIエージェントは「RAG」による外部知識の活用力、「機能呼び出し」による実行力、そして「ReAct」による試行錯誤能力を兼ね備えています。これらの技術により、金融の現場はどのように変わっていくのでしょうか。具体的な3つのシーンを見てイメージを膨らませてみましょう。
1. AIエージェントによるきめ細かなパーソナル・バンキングの支援
金融商品、特に住宅ローンや保険、相続手続きなどは、顧客一人ひとりの状況によって最適な選択肢が異なります。その際に有効なのがRAGの技術です。RAGを用いると金融機関内の膨大な商品マニュアルや規定集、過去のQ&Aなどを参照した回答の生成が可能になります。顧客に対する説明は複雑になることが多いですが、AIエージェントの導入で根拠に基づいた正確で迅速な回答を、担当者を通じて提供できるようになります。
さらにAIエージェントは、「永続メモリ」の機能、特に短期的なやりとりを記憶するエピソードメモリにより、顧客との過去の対話履歴を記憶しています。たとえば、顧客から「先日の件について、別のプランも聞きたいのですが」と問合せがあった場合でも、文脈から先日の件が何を指すのかを正確に理解してスムーズに対応案を出すことができます。まるで、顧客一人ひとりに常に注意を払ってくれる専属の担当者が付いているような、きめ細やかで質の高い顧客体験を、AIエージェントと担当者が連携して提供できます。
2. バックオフィス業務の劇的な効率化と精度向上
日々、金融機関のバックオフィスで行われる大量の事務処理。これもAIエージェントで効率的にこなすことができるでしょう。たとえば、融資審査の申し込みがあった際、これまでは担当者が提出書類を目視で確認し、必要な項目が揃っているか、入力内容に不備はないかを確認していました。
AIエージェントは、こうした定型的なチェック業務を自律的に実行できます。「機能呼び出し(Function Calling)」の仕組みを使えば、AIは単にテキストで「不備あり」と報告するだけでなく、自ら審査システムにアクセスしてステータスを更新したり、顧客に不備内容を通知するメールの下書きを作成したり、といった「行動」まで代行することもできます。
また、複数部署の人員が関わるプロジェクトの会議設定も、AIエージェントの得意分野です。関係者全員のスケジュールを参照し、最適な候補日時をいくつか提案し、参加者の承認を得て自動で各自のスケジュールを登録できます。ReActの仕組みを使い、関係者の前後の予定や移動時間などを何通りも組み合わせて最適な日程を選定します。これまで担当者がメールや電話でしていた煩雑な調整業務から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。
3. データに基づいた、一人ひとりのための資産運用提案
ウェルスマネジメント関連の業務も、AIエージェントによって大きく変わるでしょう。顧客に最適な金融商品を提案するには、その顧客の資産状況やリスク許容度、ライフステージを深く理解すると同時に、刻一刻と変わる市場の動向を把握する必要があります。
AIエージェントは、顧客の取引データ(セマンティックメモリで保持)を分析して投資傾向を把握し、「機能呼び出し」を使い外部APIから最新の市場データを取得します。さらにRAGを用いて、数多くある金融商品の目論見書やレポートを読み込み、それぞれの顧客に最適化されたポートフォリオ案を瞬時に作成します。
たとえば、「お客様は安定志向ですが、最近の市場動向から、ポートフォリオの一部をこの新興国ファンドに振り向けることで、リスクを抑えつつリターンの向上が期待できます」というような、具体的な提案が可能になり、より説得力と顧客満足度を高めた金融商品の提案ができることが期待されます。
1. AIエージェントによるきめ細かなパーソナル・バンキングの支援
金融商品、特に住宅ローンや保険、相続手続きなどは、顧客一人ひとりの状況によって最適な選択肢が異なります。その際に有効なのがRAGの技術です。RAGを用いると金融機関内の膨大な商品マニュアルや規定集、過去のQ&Aなどを参照した回答の生成が可能になります。顧客に対する説明は複雑になることが多いですが、AIエージェントの導入で根拠に基づいた正確で迅速な回答を、担当者を通じて提供できるようになります。
さらにAIエージェントは、「永続メモリ」の機能、特に短期的なやりとりを記憶するエピソードメモリにより、顧客との過去の対話履歴を記憶しています。たとえば、顧客から「先日の件について、別のプランも聞きたいのですが」と問合せがあった場合でも、文脈から先日の件が何を指すのかを正確に理解してスムーズに対応案を出すことができます。まるで、顧客一人ひとりに常に注意を払ってくれる専属の担当者が付いているような、きめ細やかで質の高い顧客体験を、AIエージェントと担当者が連携して提供できます。
2. バックオフィス業務の劇的な効率化と精度向上
日々、金融機関のバックオフィスで行われる大量の事務処理。これもAIエージェントで効率的にこなすことができるでしょう。たとえば、融資審査の申し込みがあった際、これまでは担当者が提出書類を目視で確認し、必要な項目が揃っているか、入力内容に不備はないかを確認していました。
AIエージェントは、こうした定型的なチェック業務を自律的に実行できます。「機能呼び出し(Function Calling)」の仕組みを使えば、AIは単にテキストで「不備あり」と報告するだけでなく、自ら審査システムにアクセスしてステータスを更新したり、顧客に不備内容を通知するメールの下書きを作成したり、といった「行動」まで代行することもできます。
また、複数部署の人員が関わるプロジェクトの会議設定も、AIエージェントの得意分野です。関係者全員のスケジュールを参照し、最適な候補日時をいくつか提案し、参加者の承認を得て自動で各自のスケジュールを登録できます。ReActの仕組みを使い、関係者の前後の予定や移動時間などを何通りも組み合わせて最適な日程を選定します。これまで担当者がメールや電話でしていた煩雑な調整業務から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。
3. データに基づいた、一人ひとりのための資産運用提案
ウェルスマネジメント関連の業務も、AIエージェントによって大きく変わるでしょう。顧客に最適な金融商品を提案するには、その顧客の資産状況やリスク許容度、ライフステージを深く理解すると同時に、刻一刻と変わる市場の動向を把握する必要があります。
AIエージェントは、顧客の取引データ(セマンティックメモリで保持)を分析して投資傾向を把握し、「機能呼び出し」を使い外部APIから最新の市場データを取得します。さらにRAGを用いて、数多くある金融商品の目論見書やレポートを読み込み、それぞれの顧客に最適化されたポートフォリオ案を瞬時に作成します。
たとえば、「お客様は安定志向ですが、最近の市場動向から、ポートフォリオの一部をこの新興国ファンドに振り向けることで、リスクを抑えつつリターンの向上が期待できます」というような、具体的な提案が可能になり、より説得力と顧客満足度を高めた金融商品の提案ができることが期待されます。
AIエージェント導入の現実的な課題と対策案
これまで見てきたように、AIエージェントは大きな可能性を秘めています。しかし、その導入にあたっては、いくつかの重要なリスクや課題も存在します。ここから特に金融機関が留意すべき4つのポイントを整理します。
1. 技術的なリスク:事実に基づかない回答「ハルシネーション」
課題: 大規模言語モデル(LLM)を基盤とするAIエージェントは、事実に基づかない、もっともらしい出まかせの情報を生成してしまう「ハルシネーション」のリスクを内包しています。金融商品の説明や規制に関する回答で誤情報が生成された場合、顧客の不利益やコンプライアンス違反に直結する深刻な事態を招きかねません。
対策の方向性: このリスクを軽減するには、RAGの仕組みが不可欠です。常に信頼できる金融機関内のデータベースや外部の正確な情報ソースを照会し、生成された内容をファクトチェックする検証プロセスに組み込むことが求められます。このファクトチェックには人間が関与することが望ましいと思われます。
2. 運用上のリスク:予期せぬ行動と制御の難しさ
課題: AIエージェントは自律的にタスクを遂行するがゆえに、設計者の意図を超えた行動をとる「創発的振る舞い」を起こす可能性があります。これはときにイノベーションの源泉にもなりえますが、予期せぬ取引や誤った顧客対応につながるリスクもあります。特に、後述する複数のAIエージェントが連携する環境では、一つのエージェントのエラーがシステム全体に連鎖的に波及する「エラーの連鎖」の危険性も想定されます。
対策の方向性: 対策としては、AIエージェントの権限や行動範囲をその役割に応じて明確に制限することや、その活動を常に記録・監視し、異常を即座に検知するモニタリングや監査の仕組みを構築することが考えられます。AIエージェントの利用にあたっては適切にリスクを設定し、対策を講じることが必要になります。
3. セキュリティリスク:新たな攻撃経路の出現
課題: 外部のツールやAPIと連携できるというAIエージェントの強みは、裏を返せば、そこが新たなサイバー攻撃の標的になるということでもあります。たとえば、ユーザーからの指示(プロンプト)に悪意のある命令を紛れ込ませる「プロンプトインジェクション」という攻撃により、AIエージェントを乗っ取り、内部情報への不正アクセスや不正な取引を実行させられるリスクが想定されます。
対策の方向性: API連携における厳格な認証・認可プロセスの徹底や、AIエージェントの行動を隔離された安全な環境で実行させる「サンドボックス」のような技術的対策が重要になります。
4. ガバナンス・倫理的リスク:責任の所在の曖昧さ
課題: AIエージェントが自律的に下した判断によって顧客に損害が生じた場合、「その責任はAIの開発者、運用者、それとも利用者にあるのか」という非常に複雑な問題が生じます。また、過去のデータから学習する過程で、特定の顧客層に対するバイアス(偏見)を内包してしまい、融資審査などで差別的な判断につながる倫理的なリスクも無視できません。
対策の方向性: AIの判断プロセスを後から追跡・検証可能にする「説明可能性(Explainability)」の確保が重要になります。また、融資承認のような重要な意思決定の最終判断は必ず人間が担う「ヒューマン・イン・ザ・ループ」の原則を業務プロセスに組み込むなど、ガバナンスを意識した設計思想が強く求められます。
1. 技術的なリスク:事実に基づかない回答「ハルシネーション」
課題: 大規模言語モデル(LLM)を基盤とするAIエージェントは、事実に基づかない、もっともらしい出まかせの情報を生成してしまう「ハルシネーション」のリスクを内包しています。金融商品の説明や規制に関する回答で誤情報が生成された場合、顧客の不利益やコンプライアンス違反に直結する深刻な事態を招きかねません。
対策の方向性: このリスクを軽減するには、RAGの仕組みが不可欠です。常に信頼できる金融機関内のデータベースや外部の正確な情報ソースを照会し、生成された内容をファクトチェックする検証プロセスに組み込むことが求められます。このファクトチェックには人間が関与することが望ましいと思われます。
2. 運用上のリスク:予期せぬ行動と制御の難しさ
課題: AIエージェントは自律的にタスクを遂行するがゆえに、設計者の意図を超えた行動をとる「創発的振る舞い」を起こす可能性があります。これはときにイノベーションの源泉にもなりえますが、予期せぬ取引や誤った顧客対応につながるリスクもあります。特に、後述する複数のAIエージェントが連携する環境では、一つのエージェントのエラーがシステム全体に連鎖的に波及する「エラーの連鎖」の危険性も想定されます。
対策の方向性: 対策としては、AIエージェントの権限や行動範囲をその役割に応じて明確に制限することや、その活動を常に記録・監視し、異常を即座に検知するモニタリングや監査の仕組みを構築することが考えられます。AIエージェントの利用にあたっては適切にリスクを設定し、対策を講じることが必要になります。
3. セキュリティリスク:新たな攻撃経路の出現
課題: 外部のツールやAPIと連携できるというAIエージェントの強みは、裏を返せば、そこが新たなサイバー攻撃の標的になるということでもあります。たとえば、ユーザーからの指示(プロンプト)に悪意のある命令を紛れ込ませる「プロンプトインジェクション」という攻撃により、AIエージェントを乗っ取り、内部情報への不正アクセスや不正な取引を実行させられるリスクが想定されます。
対策の方向性: API連携における厳格な認証・認可プロセスの徹底や、AIエージェントの行動を隔離された安全な環境で実行させる「サンドボックス」のような技術的対策が重要になります。
4. ガバナンス・倫理的リスク:責任の所在の曖昧さ
課題: AIエージェントが自律的に下した判断によって顧客に損害が生じた場合、「その責任はAIの開発者、運用者、それとも利用者にあるのか」という非常に複雑な問題が生じます。また、過去のデータから学習する過程で、特定の顧客層に対するバイアス(偏見)を内包してしまい、融資審査などで差別的な判断につながる倫理的なリスクも無視できません。
対策の方向性: AIの判断プロセスを後から追跡・検証可能にする「説明可能性(Explainability)」の確保が重要になります。また、融資承認のような重要な意思決定の最終判断は必ず人間が担う「ヒューマン・イン・ザ・ループ」の原則を業務プロセスに組み込むなど、ガバナンスを意識した設計思想が強く求められます。
AIエージェントが拓く自律的な金融業務
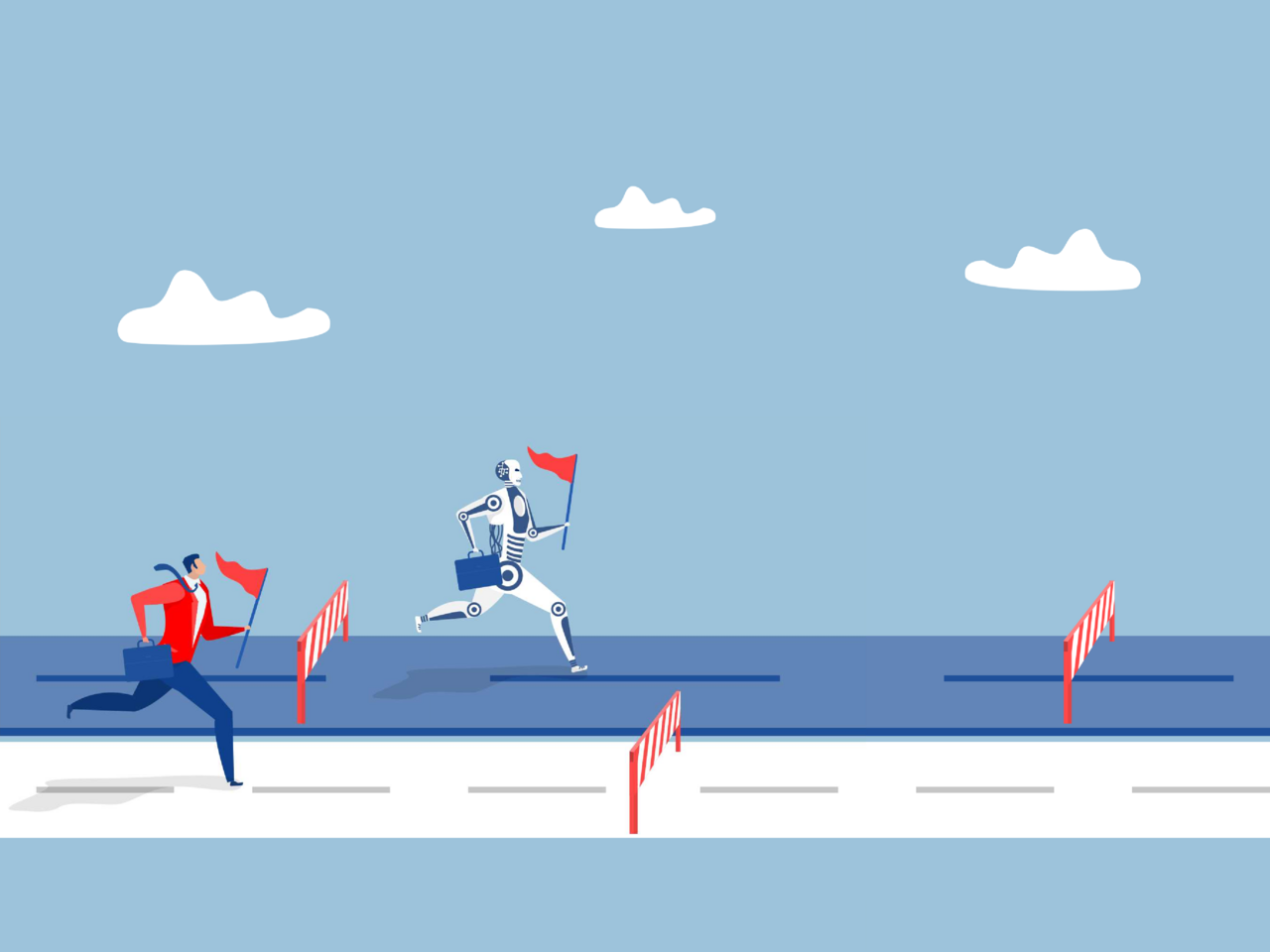
AIエージェントの活用はとても魅力的である一方、その導入には乗り越えるべき課題も数多くあります。しかし、これらのリスク管理を前提として技術が成熟したとき、「個」のAIエージェントが連携し、「チーム」として機能する、より高度な「Agentic AI(エージェンティックAI)」の時代を迎えることになります。
Agentic AIとは、単一のAIがタスクをこなすのではなく、それぞれが専門的な役割を持つ複数のAIエージェントが、指揮者(オーケストレーター)の管理下で協調し、一つの複雑な高レベル目標を達成するシステムのことです。これは、AIが「業務の代理人」から「自律的な組織」へと進化することを意味します。
例として、「AIファンドマネージャー・チーム」をあげて考えてみましょう。市場データ収集エージェントが世界中のニュースや経済指標をリアルタイムで収集・分析します。その情報をもとに、リスク分析エージェントが投資市場における天候や地政学的な要因を含むさまざまなリスクを、企業価値評価エージェントが投資対象の企業の価値を多様なデータソースをもとに評価します。
そしてポートフォリオ最適化エージェントがそれらを統合して最適な資産配分を決定し、取引実行エージェントが最良のタイミングで投資に関する投資商品等を発注します。この一連の流れをAIがチームとして動き、自律的に、かつ人間を遥かに超える速度と規模で実行できることになります。
また、金融インフラの運用が変変わっていく可能性もあります。不正検知からインシデント対応、当局への報告までを、監視エージェント、調査エージェント、報告書作成エージェントからなるAIチーム(Agentic AI)が自律的に完結させることで、より堅牢で回復力の高い金融システムが実現するかもしれません。
AIエージェントの利用が浸透すると、人間とAIの新たな協業関係の構築が必要になります。このような未来では、私たちビジネスパーソンに求められるのは、優秀なAIエージェントやAIチーム(Agentic AI)をいかに使いこなし、ビジネスの成果を最大化するかという「構想力」と「マネジメント能力」だと思われます。
定型的な業務やデータ分析はAIに「委任」し、人間は、AIでは生み出せない「新たな金融サービスの創造」や、「顧客との信頼に基づいた深い関係性の構築」、そしてAIが出した判断に対して「最終的に倫理的・経営的責任を負う」といった、人間にしかできない役割に集中していくことになるのかもしれません。
AIエージェントは、私たちの能力を拡張してくれる強力なパートナーになりえます。この新たな知能をどう活用し、顧客や社会に対してどのような価値を提供していくか、という構想を描くことが必要になってきます。
Agentic AIとは、単一のAIがタスクをこなすのではなく、それぞれが専門的な役割を持つ複数のAIエージェントが、指揮者(オーケストレーター)の管理下で協調し、一つの複雑な高レベル目標を達成するシステムのことです。これは、AIが「業務の代理人」から「自律的な組織」へと進化することを意味します。
例として、「AIファンドマネージャー・チーム」をあげて考えてみましょう。市場データ収集エージェントが世界中のニュースや経済指標をリアルタイムで収集・分析します。その情報をもとに、リスク分析エージェントが投資市場における天候や地政学的な要因を含むさまざまなリスクを、企業価値評価エージェントが投資対象の企業の価値を多様なデータソースをもとに評価します。
そしてポートフォリオ最適化エージェントがそれらを統合して最適な資産配分を決定し、取引実行エージェントが最良のタイミングで投資に関する投資商品等を発注します。この一連の流れをAIがチームとして動き、自律的に、かつ人間を遥かに超える速度と規模で実行できることになります。
また、金融インフラの運用が変変わっていく可能性もあります。不正検知からインシデント対応、当局への報告までを、監視エージェント、調査エージェント、報告書作成エージェントからなるAIチーム(Agentic AI)が自律的に完結させることで、より堅牢で回復力の高い金融システムが実現するかもしれません。
AIエージェントの利用が浸透すると、人間とAIの新たな協業関係の構築が必要になります。このような未来では、私たちビジネスパーソンに求められるのは、優秀なAIエージェントやAIチーム(Agentic AI)をいかに使いこなし、ビジネスの成果を最大化するかという「構想力」と「マネジメント能力」だと思われます。
定型的な業務やデータ分析はAIに「委任」し、人間は、AIでは生み出せない「新たな金融サービスの創造」や、「顧客との信頼に基づいた深い関係性の構築」、そしてAIが出した判断に対して「最終的に倫理的・経営的責任を負う」といった、人間にしかできない役割に集中していくことになるのかもしれません。
AIエージェントは、私たちの能力を拡張してくれる強力なパートナーになりえます。この新たな知能をどう活用し、顧客や社会に対してどのような価値を提供していくか、という構想を描くことが必要になってきます。
※本記事の内容は、執筆者が所属する会社・団体の意見を代表するものではありません。
※記事中の所属・役職名は執筆当時のものです。


 X
X















